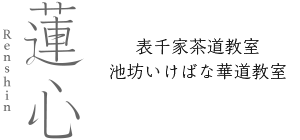松露庵「蓮心会 お茶会」のご案内
今年の桜は 60年ぶりに早いとか? その影響か全ての花が同じように早く咲いているようです。
さて、一年半前に 田無教室で「茶会・花展」を開いて以来、私たちにとって初めて本格的な茶室を借りての「茶会」を今月末に開催します。
以前、このブログで「茶事・茶会・添釜」の区別は説明していますので この場では控えますが、
「茶会」に慣れていない 私たちが開く「茶会」。
『茶道は敷居が高い!』、『着物が着れない!』、『正座が苦手!』と敬遠している方にこそ
茶道の魅力をお伝えしたい想いから開催する茶会ですので、初めての方や、海外の方も大歓迎!
是非、この機会に 日本文化を楽しく学んでください。
全てお伝えしますし、用意もありますので 何も知らない方でも全く問題ありません。
以下をご覧になり、参加ご希望の方は 「問い合わせフォーム」よりお申し込みください。
不明な点は 詳しく説明いたします。
*日時:平成三十年 四月三十日(祝)
*各回予約制ですので 希望時間の第一希望と第二希望を以下からお知らせください。
*各回15分前が集合時間です。
① 11時から11時45分
② 12時から12時45分
③ 13時から13時45分
*場所:松露庵茶室
東京都武蔵野市桜堤1-4−22(私立古瀬公園内)駐車場はありません。
旧古瀬邸を改修した、趣きある茶室です。
*茶券:千円(和菓子・抹茶)
*ご予約は、お名前・ご連絡先(ご住所)・ご希望時間・人数を明記の上お申し込みください。
*ご予約が完了しましたら、茶券と地図をお送りいたします。
*正座が苦手な方には座椅子のご用意もございます。遠慮なくお申し付けください。
日頃の稽古の稽古の成果を精一杯発揮して社中一同 皆様のお越しをお待ちしています。
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
さて、一年半前に 田無教室で「茶会・花展」を開いて以来、私たちにとって初めて本格的な茶室を借りての「茶会」を今月末に開催します。
以前、このブログで「茶事・茶会・添釜」の区別は説明していますので この場では控えますが、
「茶会」に慣れていない 私たちが開く「茶会」。
『茶道は敷居が高い!』、『着物が着れない!』、『正座が苦手!』と敬遠している方にこそ
茶道の魅力をお伝えしたい想いから開催する茶会ですので、初めての方や、海外の方も大歓迎!
是非、この機会に 日本文化を楽しく学んでください。
全てお伝えしますし、用意もありますので 何も知らない方でも全く問題ありません。
以下をご覧になり、参加ご希望の方は 「問い合わせフォーム」よりお申し込みください。
不明な点は 詳しく説明いたします。
*日時:平成三十年 四月三十日(祝)
*各回予約制ですので 希望時間の第一希望と第二希望を以下からお知らせください。
*各回15分前が集合時間です。
① 11時から11時45分
② 12時から12時45分
③ 13時から13時45分
*場所:松露庵茶室
東京都武蔵野市桜堤1-4−22(私立古瀬公園内)駐車場はありません。
旧古瀬邸を改修した、趣きある茶室です。
*茶券:千円(和菓子・抹茶)
*ご予約は、お名前・ご連絡先(ご住所)・ご希望時間・人数を明記の上お申し込みください。
*ご予約が完了しましたら、茶券と地図をお送りいたします。
*正座が苦手な方には座椅子のご用意もございます。遠慮なくお申し付けください。
日頃の稽古の稽古の成果を精一杯発揮して社中一同 皆様のお越しをお待ちしています。
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
IAC 駒場前田邸迎賓館茶会 レポート
2017年3月に開催した IAC(国際芸術家センター)主催、「リトアニア大使夫人と共に学ぶ茶事と懐石@駒場前田邸迎賓館」の様子がアップされたので、報告します。
(と、公開していたつもりでしたが、IAC側のアップを待つうちに忘れてしまい、投稿されていなかったことに今気がつきまいした。)
開催予告とともに満席となる好評をいただいてるこの企画、2018年も3月11日に開催します。すっかり遅くなりましたが 昨年の報告をご覧ください。
掛物は、「福寿海無量(ふくじゅかいむりょう)」。『観音経』の中にある一句です。観世音菩薩の功徳は「福を聚めた大きな海のように深く無量にある」という意味の言葉です。
今日は大使夫人を迎え 皆で集まることの出来た喜びの想い、喜びの気持ちを この掛物に込めました。
当日は「お彼岸」の最中でしたので、お花を「彼岸桜」にしました。染井吉野より、ひと足早く咲く桜に これから迎える春の華やかさを感じてもらいたいと思い選びました。
書院の床の間なので本来は重厚感のある花入れが良いのですが、京都から立派な青竹が手に入りましたので「青竹」に。切りたての竹の青さは、その時一度きりなのでどの器よりご馳走を表せると云います。庭に咲いた「貝母(バイモ)」という可憐な草花を添えてました。
『茶花は野にあるように かろがろ と生けよ』と利休の言葉が残っています。
茶花は、その地方の旬の花を生けて、お客様を迎える心が大切です。
お菓子は「松風(まつかぜ)」。京都の老舗菓子屋「亀屋陸奥」。このお菓子は、信長と石山本願寺の11年続いた合戦のさなかに 兵糧として考案されたという いにしえの菓子です。
お菓子にちなんで お点前の道具も「旅箪笥」という 棚に。
今の時代では、まるで春の麗らかな野点を連想させますが、実はこの棚は 秀吉が小田原征伐の折、利休に命じて考案させたものなのです。
この棚に、水指や茶器、柄杓、蓋置など、お茶を点てるのに必要な道具を全て収納して 担いで運べるように工夫されています。
明日の命が約束されない戦国時代、男性達はどんな心でお茶一服を戴いていたのでしょうか。。
「嫁入り前の習い物」 と思われがちな「茶道や華道」ですが、実は「男性が命がけで培ってきた日本の美意識の集大成」ということを 少しでも伝えられたら、と思い 室礼を考えました。
こうした集まりで、「四季折々を楽しめる日本の素晴らしさ」を、体感していただけたら幸せに思います。
この日はわたしも 皆様と 歴史ある建物のなかで 心豊かな時間を過ごすことが出来ました。
IACのブログです↓
http://iactokyo.jp/2017/04/25/teacelemony_komaba_0320/
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
(と、公開していたつもりでしたが、IAC側のアップを待つうちに忘れてしまい、投稿されていなかったことに今気がつきまいした。)
開催予告とともに満席となる好評をいただいてるこの企画、2018年も3月11日に開催します。すっかり遅くなりましたが 昨年の報告をご覧ください。
掛物は、「福寿海無量(ふくじゅかいむりょう)」。『観音経』の中にある一句です。観世音菩薩の功徳は「福を聚めた大きな海のように深く無量にある」という意味の言葉です。
今日は大使夫人を迎え 皆で集まることの出来た喜びの想い、喜びの気持ちを この掛物に込めました。
当日は「お彼岸」の最中でしたので、お花を「彼岸桜」にしました。染井吉野より、ひと足早く咲く桜に これから迎える春の華やかさを感じてもらいたいと思い選びました。
書院の床の間なので本来は重厚感のある花入れが良いのですが、京都から立派な青竹が手に入りましたので「青竹」に。切りたての竹の青さは、その時一度きりなのでどの器よりご馳走を表せると云います。庭に咲いた「貝母(バイモ)」という可憐な草花を添えてました。
『茶花は野にあるように かろがろ と生けよ』と利休の言葉が残っています。
茶花は、その地方の旬の花を生けて、お客様を迎える心が大切です。
お菓子は「松風(まつかぜ)」。京都の老舗菓子屋「亀屋陸奥」。このお菓子は、信長と石山本願寺の11年続いた合戦のさなかに 兵糧として考案されたという いにしえの菓子です。
お菓子にちなんで お点前の道具も「旅箪笥」という 棚に。
今の時代では、まるで春の麗らかな野点を連想させますが、実はこの棚は 秀吉が小田原征伐の折、利休に命じて考案させたものなのです。
この棚に、水指や茶器、柄杓、蓋置など、お茶を点てるのに必要な道具を全て収納して 担いで運べるように工夫されています。
明日の命が約束されない戦国時代、男性達はどんな心でお茶一服を戴いていたのでしょうか。。
「嫁入り前の習い物」 と思われがちな「茶道や華道」ですが、実は「男性が命がけで培ってきた日本の美意識の集大成」ということを 少しでも伝えられたら、と思い 室礼を考えました。
こうした集まりで、「四季折々を楽しめる日本の素晴らしさ」を、体感していただけたら幸せに思います。
この日はわたしも 皆様と 歴史ある建物のなかで 心豊かな時間を過ごすことが出来ました。
IACのブログです↓
http://iactokyo.jp/2017/04/25/teacelemony_komaba_0320/
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
外国人の方へ「茶事」で おもてなし
『今、日本がクール! 』 京都は勿論、富士山、秋葉原、、昨年日本を訪れた外国人は約2.400万人。わずか5年で3倍に増えたそうです。身近な街のあちこちで日々観光客を見かけるようになりましたね。2020年の東京五輪へ向けて私たちはさらに多くの外国人を迎えることになるでしょう。
思いおこせば数年前 我が家でも、学芸大学の交換留学生30名位のへ茶道指導をしました。「座禅(呼吸法)」「茶庭からの席入り」「茶道の歴史」「茶室での礼法(炭点前・拝見の仕方・それぞれの意味)」「二人一組で実際に一服点て、いただききあう礼法の体験」などを行いました。『日本は素敵!』と若き学生たちが語るキラキラした瞳が印象的でした。
個人的にも10年以上前から友人の依頼で、スペイン、ドイツ、イギリスなど各国の客人への茶道体験を開いています。華道でも 日本の大学生へ華道講師をさせていただいたり 華道ワークショップを開いたりして日本の文化を伝えることをし続けています。その経験を通して私が一番感じることは、『多くの日本人が自国の文化を知らないでいる』ということです。
実は私、1987年(丁度30年前ですね) NYへ遊学しました。たった2~3ヶ月程でしたが、その時現地で知り合った日本人が あまりに日本の文化を知らないまま外国で暮らしていることに とてもショックを受けました。茶道・華道を習い始めていた私は、『どの国の文化もそれぞれに素晴らしい。でも真の国際交流とは、まず自国の文化を知り、紹介しあうことから始まるのでは?』と気付いたのです。
『これから益々、世界へ旅立つ日本人が増えるはず。そうした方々へ私が茶道・華道を伝えていけるよう学ぼう』と決意し帰国。夢中で稽古を重ね 今の私がいます。が、30年経ちその状況は当時より改善されているのでしょうか? (一概に言えませんが)英会話に堪能な人は増えても文化を学ぶ人は減少しているのではないかと感じます。そうだとすると とても残念なことです。
我が家の教室では2年程前から中国人(日本語堪能)が数名稽古へ来ています。彼女たちと話をしていて気が付いたことがあります。
一人の生徒が云いました。『私は日本へ留学したくて必死に日本語を勉強してきました。そして日本に住むことが出来た今、中国のことが大好きな方々が私に中国の歴史などを詳しく聞いてきます。しかし、私は自国 中国のことをあまり勉強してきませんでした。それが今、恥ずかしいです。』と。
それを聞いた時に、どこの国でも同じなんだと分かりました。そして、日本人に伝えたい と こだわることを止めました。時間はかかるかもしれないけれど、私は国籍は関係なく 伝統文化「茶道・華道」を学びたい体験したいと願う方へこの素晴らしい文化を正しく伝えていくことが大切なんだと決意を新たにしました。思えば、日本人は昔から自国の良きものの多くを外国の方から教えられて気が付いています。上高地や桂離宮に代表される観光地や仏像・絵画もしかり。最近は盆栽も、外国の方の『クール!』で見直されていますものね。
今年九月、生徒の友人から「海外から来日する西洋からの外国人を茶道で もてなしてほしい。」との依頼を受けました。依頼者の日本の方々も茶道を全く知らないので一緒に参加したい とのことでした。
茶道のおもてなしの極意は「茶事」です。せっかくなら表面的なことだけではなく、今までの私の経験を駆使し工夫すれば茶道の極意を体感していただけるのではないか、と内容を企画。
丁度同時期に 中国から一週間集中稽古のために来日する中国人女性と、スペインへ転勤する前の二ヶ月短期学習に学びに日本人女性が来ていたので、その生徒達にもこれは一番の勉強になると 平日に二週連続で「茶事(ダイジェスト版)の会」を開催しました。
内容は、正式な茶事の流れを体験してもらうもので、①「寄付き」②「茶庭で蹲踞を使用し席入り・拝見・挨拶」③「炭点前・炭や香合の説明」④「一汁一菜の精進茶懐石と一献」⑤「濃茶・続き薄」。最後に「質疑応答」と「記念撮影」。
外国の方は正座が出来ませんから椅子も用意し、時間をかけないことに留意しました。
写真は ④の精進料理の一部、一膳の内容は「玉蜀黍ご飯、昆布の出汁椀にとろろ昆布と刻んだ枝豆と梅干し、向こう付けは、胡麻豆腐(下に自家製味噌)。」
煮物椀の代わりに八寸「昆布の素揚げと、獅子唐」と日本酒。


全て私の手作り。当日の半東にはこれらの作り方を教えました。
両日とも、お客様からは『茶道の奥深さを感じることが出来た』と 大感動・大満足していただけました。なかなか、お開き出来ないくらい沢山の感謝の言葉を頂きました。
西洋の方々(6名)には写真撮影も構わないと伝えたのですが、静かに流れる時間に感動してくださり、シャッター音の全くしない茶の湯の時間を全身で味わってくださいました。
中国人女性と日本人女性と私で一緒に露地で撮影した写真はあります。とても神秘的。

 華道の稽古も2回。
華道の稽古も2回。
写真右上の中国から一週間茶道と華道の稽古のためだけに来日していたECHO (余 紅梅)さんは、日本語は勿論 ほとんど英語も話せないなか、六日間 身振り手振りで伝える私の厳しい稽古に一所懸命ついてきました。


そうして、最終日にお礼をしたいと 中国茶の儀式を披露してくれました。
それが、とても本格的で同じお茶の葉を時間をかけて何度も味わい、その違いを楽しむ式法でした。私達の茶道の式法より長い時間を要します。その儀式に参加し拝見している時に、納得できました。彼女は住んでいる場所は違っても 同じ「道」を極める同士だから この一週間を乗り越えられたのだと。
素晴らしい出会いであり、私にとっても深い勉強でした。
茶道の世界、深さを言葉で説明することはとても難しいです。私は残念ながら英会話はほとんど忘れてしまいましたが、大切なことは「感じる」こと、と信じています。絵画を観る時も私たちは頭で理解しようとしていませんものね。
私が外国の方へ、あえて「茶道(茶事ダイジェスト版)の会」で 日本のおもてなしをしたい理由は、言葉を超えた何かを感じてもらいたいから。
身体で感じ 感動することで、もう一歩先を覗いてみたい そしてそれを「知りたい」と突き動かされるものだと思うから。そんな一瞬を感じていただきたい。それが趣旨です。
最近、外国人に日本文化を紹介する(インバウンドと言うのですね)「Vacation Japan」『日本の伝統文化スペシャリスト(茶道・華道)』に登録されました。外国の方から直接アポが来るそうです。どうしましょう(笑)
少しは英会話を勉強し直さなくてはなりませんね? いやいや、自信ないなぁ・・
ん? 継続は力?・・はい。 頑張ります(汗;)
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
思いおこせば数年前 我が家でも、学芸大学の交換留学生30名位のへ茶道指導をしました。「座禅(呼吸法)」「茶庭からの席入り」「茶道の歴史」「茶室での礼法(炭点前・拝見の仕方・それぞれの意味)」「二人一組で実際に一服点て、いただききあう礼法の体験」などを行いました。『日本は素敵!』と若き学生たちが語るキラキラした瞳が印象的でした。
個人的にも10年以上前から友人の依頼で、スペイン、ドイツ、イギリスなど各国の客人への茶道体験を開いています。華道でも 日本の大学生へ華道講師をさせていただいたり 華道ワークショップを開いたりして日本の文化を伝えることをし続けています。その経験を通して私が一番感じることは、『多くの日本人が自国の文化を知らないでいる』ということです。
実は私、1987年(丁度30年前ですね) NYへ遊学しました。たった2~3ヶ月程でしたが、その時現地で知り合った日本人が あまりに日本の文化を知らないまま外国で暮らしていることに とてもショックを受けました。茶道・華道を習い始めていた私は、『どの国の文化もそれぞれに素晴らしい。でも真の国際交流とは、まず自国の文化を知り、紹介しあうことから始まるのでは?』と気付いたのです。
『これから益々、世界へ旅立つ日本人が増えるはず。そうした方々へ私が茶道・華道を伝えていけるよう学ぼう』と決意し帰国。夢中で稽古を重ね 今の私がいます。が、30年経ちその状況は当時より改善されているのでしょうか? (一概に言えませんが)英会話に堪能な人は増えても文化を学ぶ人は減少しているのではないかと感じます。そうだとすると とても残念なことです。
我が家の教室では2年程前から中国人(日本語堪能)が数名稽古へ来ています。彼女たちと話をしていて気が付いたことがあります。
一人の生徒が云いました。『私は日本へ留学したくて必死に日本語を勉強してきました。そして日本に住むことが出来た今、中国のことが大好きな方々が私に中国の歴史などを詳しく聞いてきます。しかし、私は自国 中国のことをあまり勉強してきませんでした。それが今、恥ずかしいです。』と。
それを聞いた時に、どこの国でも同じなんだと分かりました。そして、日本人に伝えたい と こだわることを止めました。時間はかかるかもしれないけれど、私は国籍は関係なく 伝統文化「茶道・華道」を学びたい体験したいと願う方へこの素晴らしい文化を正しく伝えていくことが大切なんだと決意を新たにしました。思えば、日本人は昔から自国の良きものの多くを外国の方から教えられて気が付いています。上高地や桂離宮に代表される観光地や仏像・絵画もしかり。最近は盆栽も、外国の方の『クール!』で見直されていますものね。
今年九月、生徒の友人から「海外から来日する西洋からの外国人を茶道で もてなしてほしい。」との依頼を受けました。依頼者の日本の方々も茶道を全く知らないので一緒に参加したい とのことでした。
茶道のおもてなしの極意は「茶事」です。せっかくなら表面的なことだけではなく、今までの私の経験を駆使し工夫すれば茶道の極意を体感していただけるのではないか、と内容を企画。
丁度同時期に 中国から一週間集中稽古のために来日する中国人女性と、スペインへ転勤する前の二ヶ月短期学習に学びに日本人女性が来ていたので、その生徒達にもこれは一番の勉強になると 平日に二週連続で「茶事(ダイジェスト版)の会」を開催しました。
内容は、正式な茶事の流れを体験してもらうもので、①「寄付き」②「茶庭で蹲踞を使用し席入り・拝見・挨拶」③「炭点前・炭や香合の説明」④「一汁一菜の精進茶懐石と一献」⑤「濃茶・続き薄」。最後に「質疑応答」と「記念撮影」。
外国の方は正座が出来ませんから椅子も用意し、時間をかけないことに留意しました。
写真は ④の精進料理の一部、一膳の内容は「玉蜀黍ご飯、昆布の出汁椀にとろろ昆布と刻んだ枝豆と梅干し、向こう付けは、胡麻豆腐(下に自家製味噌)。」
煮物椀の代わりに八寸「昆布の素揚げと、獅子唐」と日本酒。


全て私の手作り。当日の半東にはこれらの作り方を教えました。
両日とも、お客様からは『茶道の奥深さを感じることが出来た』と 大感動・大満足していただけました。なかなか、お開き出来ないくらい沢山の感謝の言葉を頂きました。
西洋の方々(6名)には写真撮影も構わないと伝えたのですが、静かに流れる時間に感動してくださり、シャッター音の全くしない茶の湯の時間を全身で味わってくださいました。
中国人女性と日本人女性と私で一緒に露地で撮影した写真はあります。とても神秘的。

 華道の稽古も2回。
華道の稽古も2回。写真右上の中国から一週間茶道と華道の稽古のためだけに来日していたECHO (余 紅梅)さんは、日本語は勿論 ほとんど英語も話せないなか、六日間 身振り手振りで伝える私の厳しい稽古に一所懸命ついてきました。


そうして、最終日にお礼をしたいと 中国茶の儀式を披露してくれました。
それが、とても本格的で同じお茶の葉を時間をかけて何度も味わい、その違いを楽しむ式法でした。私達の茶道の式法より長い時間を要します。その儀式に参加し拝見している時に、納得できました。彼女は住んでいる場所は違っても 同じ「道」を極める同士だから この一週間を乗り越えられたのだと。
素晴らしい出会いであり、私にとっても深い勉強でした。
茶道の世界、深さを言葉で説明することはとても難しいです。私は残念ながら英会話はほとんど忘れてしまいましたが、大切なことは「感じる」こと、と信じています。絵画を観る時も私たちは頭で理解しようとしていませんものね。
私が外国の方へ、あえて「茶道(茶事ダイジェスト版)の会」で 日本のおもてなしをしたい理由は、言葉を超えた何かを感じてもらいたいから。
身体で感じ 感動することで、もう一歩先を覗いてみたい そしてそれを「知りたい」と突き動かされるものだと思うから。そんな一瞬を感じていただきたい。それが趣旨です。
最近、外国人に日本文化を紹介する(インバウンドと言うのですね)「Vacation Japan」『日本の伝統文化スペシャリスト(茶道・華道)』に登録されました。外国の方から直接アポが来るそうです。どうしましょう(笑)
少しは英会話を勉強し直さなくてはなりませんね? いやいや、自信ないなぁ・・
ん? 継続は力?・・はい。 頑張ります(汗;)
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
「茶事」と「茶会」について
前回、「茶事」・「朝茶」とは? を 書きました。
では「茶会」とは? も説明しておこうかと思うので、書き足しておきます。
「茶事」とは、客を招いて、懐石・濃茶・薄茶をもてなす正式な茶のこと と説明しました。
我が家では基本的に、「初釜」と「朝茶」を開きますが、茶事自体は亭主の目的により、いつ、なんどきに開いても良いものです。
初秋の夕方に行う「夕ざりの茶事」、冬の夜長を楽しむ「曙の茶事」や「夜咄(よばなし)」。夜の闇の中で蝋燭の明かりを手がかりに運ばれる茶事は、ベテランならではの醍醐味があります。
11月初旬には、茶壺の口を開ける「口切り」の茶事。今の時代はいつでも抹茶を購入できますが、昔はその家の一年分の葉茶を5月に茶園で摘み、茶壺に入れて発酵させ 立冬を過ぎた頃、開けるのです。一年に一回のその御宅の新茶を開ける瞬間に立ち会える茶事ですから、茶の正月と呼ばれるとてもおめでたい会です。
他には、参加できない茶事のその流れを味わう「跡見の茶事」、食事を省略する「飯後の茶事」、不意に訪れた客をもてなす「不時の茶事」、などなど。
「祝い、追善、雪月花、行事、季節、時刻、趣向」を軸に必ずなんのために催す茶事なのか、その目的それぞれの趣向で開かれます。亭主は、その目的に沿った道具組み、献立、客組みを考え準備します。
亭主は、客にはあらかじめ説明し、了解をとった上で 改めて書状で案内狀を出します。そこにその茶事の趣旨と日時、場所、連客の氏名などが明記されています。
客の心得としては、受けた案内に対して 参、不参の返事をし 万難を排して出席する覚悟を持ちます。
考え方としては、結婚式に招かれたと同じことと捉えたらわかりやすいでしょう。同じことです。
ここまで書くと、「茶会」との違いがわかりやすいと思います。
「茶会」というのは、「大寄せ」とも云われるように茶道を学んでいる方もそうでない方も、興味のある方大勢がお見えになり、一緒に抹茶一服を頂くことができる場です。
茶会へ行きたい方は、茶券を購入し(数千円から数万円)、会場でその部屋に沿った人数で席入りし、お菓子とお茶をいただき、道具を拝見して楽しみます。
茶席は一席おあれば、4〜5席など大きなものまで様々。各席に席主という席をかけた方がいて、それぞれの茶室の室礼などを気軽に楽しむことができます。
京都の大徳寺では、毎月利休様の命日 28日に、「月釜」という茶会が開かれています。とてもレベルの高い茶会ですが、どなたでも参加することができます。
春、秋の外が気持ちの良い季節気持ちの良いには、「野点」という茶会もあります。
また、陶器など作家さんの展覧会や、文化的発表会などに 茶の湯で華を添える「添釜」も。
百貨店などで見かけた方も多いのではないでしょうか?
私の教室では例年2月に開かれる「新年能」の会で 添釜をしています。
招かれた方のみ(経験の有無は問いません)で開かれる最も正式な「茶事」。
券を購入しどなたでも参加できる「茶会」や、その場で楽しめる「添釜」。
どれも「粗茶一服」の姿勢には変わりませんが、茶の湯の本質に触れるのは「茶事」といえるでしょう。
写真が見つかったら、いつか追加しておきますね。
まだ 『想像がつかない!』と 思われた方、是非体験へいらしてください。『百聞は一見に如かず』です。
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
では「茶会」とは? も説明しておこうかと思うので、書き足しておきます。
「茶事」とは、客を招いて、懐石・濃茶・薄茶をもてなす正式な茶のこと と説明しました。
我が家では基本的に、「初釜」と「朝茶」を開きますが、茶事自体は亭主の目的により、いつ、なんどきに開いても良いものです。
初秋の夕方に行う「夕ざりの茶事」、冬の夜長を楽しむ「曙の茶事」や「夜咄(よばなし)」。夜の闇の中で蝋燭の明かりを手がかりに運ばれる茶事は、ベテランならではの醍醐味があります。
11月初旬には、茶壺の口を開ける「口切り」の茶事。今の時代はいつでも抹茶を購入できますが、昔はその家の一年分の葉茶を5月に茶園で摘み、茶壺に入れて発酵させ 立冬を過ぎた頃、開けるのです。一年に一回のその御宅の新茶を開ける瞬間に立ち会える茶事ですから、茶の正月と呼ばれるとてもおめでたい会です。
他には、参加できない茶事のその流れを味わう「跡見の茶事」、食事を省略する「飯後の茶事」、不意に訪れた客をもてなす「不時の茶事」、などなど。
「祝い、追善、雪月花、行事、季節、時刻、趣向」を軸に必ずなんのために催す茶事なのか、その目的それぞれの趣向で開かれます。亭主は、その目的に沿った道具組み、献立、客組みを考え準備します。
亭主は、客にはあらかじめ説明し、了解をとった上で 改めて書状で案内狀を出します。そこにその茶事の趣旨と日時、場所、連客の氏名などが明記されています。
客の心得としては、受けた案内に対して 参、不参の返事をし 万難を排して出席する覚悟を持ちます。
考え方としては、結婚式に招かれたと同じことと捉えたらわかりやすいでしょう。同じことです。
ここまで書くと、「茶会」との違いがわかりやすいと思います。
「茶会」というのは、「大寄せ」とも云われるように茶道を学んでいる方もそうでない方も、興味のある方大勢がお見えになり、一緒に抹茶一服を頂くことができる場です。
茶会へ行きたい方は、茶券を購入し(数千円から数万円)、会場でその部屋に沿った人数で席入りし、お菓子とお茶をいただき、道具を拝見して楽しみます。
茶席は一席おあれば、4〜5席など大きなものまで様々。各席に席主という席をかけた方がいて、それぞれの茶室の室礼などを気軽に楽しむことができます。
京都の大徳寺では、毎月利休様の命日 28日に、「月釜」という茶会が開かれています。とてもレベルの高い茶会ですが、どなたでも参加することができます。
春、秋の外が気持ちの良い季節気持ちの良いには、「野点」という茶会もあります。
また、陶器など作家さんの展覧会や、文化的発表会などに 茶の湯で華を添える「添釜」も。
百貨店などで見かけた方も多いのではないでしょうか?
私の教室では例年2月に開かれる「新年能」の会で 添釜をしています。
招かれた方のみ(経験の有無は問いません)で開かれる最も正式な「茶事」。
券を購入しどなたでも参加できる「茶会」や、その場で楽しめる「添釜」。
どれも「粗茶一服」の姿勢には変わりませんが、茶の湯の本質に触れるのは「茶事」といえるでしょう。
写真が見つかったら、いつか追加しておきますね。
まだ 『想像がつかない!』と 思われた方、是非体験へいらしてください。『百聞は一見に如かず』です。
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
「朝茶」「茶事」とは?
我が家の茶道教室では、年に二回「茶事」を開催します。
冬は2月初めに「初釜」、夏は8月初めに「朝茶」を開くことにしてます。
そこで 今回はこの「茶事」について少し書いておこうと思います。
さて、「茶事」とは?
「茶事」とは、一般に 懐石料理といわれる茶の湯のための料理を伴った茶のもてなしのこと。
客をもてなす丁寧な形式の茶の湯で、正式な茶の湯のことでもあります。
「正式な茶の湯」とは、濃茶をもてなすことを中心に、その濃茶を美味しく点てられるために炉や風炉に炭をつぐ「炭点前」をし、濃茶を美味しく味わっていただくための料理をすすめ、また濃茶だけでなく、薄茶をもてなす仕組みです。
その「茶事」の基本となっているのが「炉の正午の茶事」と云われる手順です。
茶事に招かれ、当日定刻少し前に亭主宅や会場へ伺います。
先ず初めに「寄付き」と呼ばれる部屋で、身支度を整え、連客と挨拶したり
客が揃うまで寄付きを拝見して待ちます。
亭主側の方から「露地」へ移動するよう促されます。露地で、気持ちを整えて待ちます。
亭主の「迎えつけ」と云われる挨拶があります。茶事は、ここからがスタートです。

 客側からみた順序としては、
客側からみた順序としては、
一、初炭
亭主が炭点前をし、釜の湯を沸かします。使われる炭道具や香の入れ物「香合」を拝見します。

二、懐石
一汁一菜から一汁三菜。また点心やお弁当など趣旨・趣向により工夫されます。
お酒とともにいただきます。
三、菓子・中立ち
茶懐石の最後にデザートとして主菓子が出ます。その後、席改のために露地へ移ります。


四、濃茶
茶事のメインである濃茶を亭主が点ててくださります。床の間には茶花が。


五、後炭
炭の力が落ちてきますので、炭を継ぎたす炭点前。
六、薄茶
メインの濃茶が終わり、すぐお開きというのも名残惜しいので、干菓子と薄茶をいただき
和やかに過ごします。記念に写真撮影もあるでしょう。
亭主とはこの部屋でお別れです。客は露地を通り、寄付きに戻り身支度を整え帰宅します。
この間、約四〜五時間。でも、あっという間に感じます。
この炉の正午の茶事の順を基本に、「朝茶」「前茶」などのバリエーションがあります。
「朝茶」とは、七月や八月の猛暑の昼に客を招くことが無理な時節、五時や六時の早朝から九時〜十時、日が高くなる前の「夏の涼気を楽しむ」という心意気から生まれたもの。
暑気払いの効果や、暑い季節だからこその道具やしつらえを味わい、季節とともに歩むのを楽しむ茶事です。
特徴として、夏の早朝、釜に清新な朝の水をつぐという所作、懐石の料理も夏の朝ですから、焼き物は省き生の魚は使わない「一汁二菜」。
丁寧で正式を軸に 朝茶では、「初炭」「懐石」「菓子・中立ち」「濃茶・続き薄茶」という順序で、「後炭」を省略し、濃茶と薄茶を続けて点てることで時間を短縮し、サラサラと進めることが信条です。
夏のご馳走は「水」。亭主は、前夜からしっかりと道や露地に水を打ち、準備を始めます。
お客様には マイナスイオンたっぷりの露地や、夏ならではの道具の取り合わや花、献立を楽しみ、メインである濃茶を皆で味わっていただきたいです。
普段の稽古はこの「茶事」を楽しむ作法や心を学ぶもの。ですから、茶事は稽古の集大成。とはいえ この茶事は、どの段階でも客として楽しむことができます。本当の「日本のおもてなし」を体感できます。
今夏は、稽古社中は勿論、懐石料理を協力していただいいる割烹料理店の若手スタッフ三名、昨年からタイに転勤している華道の弟子、主人が経営するスペインレストランへアルバイトで来ている交換留学生のスペイン人女性と体験の方も大勢参加します。私はまさに今、準備に追われていますが、この生みの苦しみ無くして 成功はないので頑張ります!
「茶の湯こそ せぬひともなき手すさみの 心のするは世にもまれなり」/道安(利休の息子)
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
冬は2月初めに「初釜」、夏は8月初めに「朝茶」を開くことにしてます。
そこで 今回はこの「茶事」について少し書いておこうと思います。
さて、「茶事」とは?
「茶事」とは、一般に 懐石料理といわれる茶の湯のための料理を伴った茶のもてなしのこと。
客をもてなす丁寧な形式の茶の湯で、正式な茶の湯のことでもあります。
「正式な茶の湯」とは、濃茶をもてなすことを中心に、その濃茶を美味しく点てられるために炉や風炉に炭をつぐ「炭点前」をし、濃茶を美味しく味わっていただくための料理をすすめ、また濃茶だけでなく、薄茶をもてなす仕組みです。
その「茶事」の基本となっているのが「炉の正午の茶事」と云われる手順です。
茶事に招かれ、当日定刻少し前に亭主宅や会場へ伺います。
先ず初めに「寄付き」と呼ばれる部屋で、身支度を整え、連客と挨拶したり
客が揃うまで寄付きを拝見して待ちます。
亭主側の方から「露地」へ移動するよう促されます。露地で、気持ちを整えて待ちます。
亭主の「迎えつけ」と云われる挨拶があります。茶事は、ここからがスタートです。

 客側からみた順序としては、
客側からみた順序としては、一、初炭
亭主が炭点前をし、釜の湯を沸かします。使われる炭道具や香の入れ物「香合」を拝見します。

二、懐石
一汁一菜から一汁三菜。また点心やお弁当など趣旨・趣向により工夫されます。
お酒とともにいただきます。

三、菓子・中立ち
茶懐石の最後にデザートとして主菓子が出ます。その後、席改のために露地へ移ります。


四、濃茶
茶事のメインである濃茶を亭主が点ててくださります。床の間には茶花が。


五、後炭
炭の力が落ちてきますので、炭を継ぎたす炭点前。
六、薄茶
メインの濃茶が終わり、すぐお開きというのも名残惜しいので、干菓子と薄茶をいただき
和やかに過ごします。記念に写真撮影もあるでしょう。
亭主とはこの部屋でお別れです。客は露地を通り、寄付きに戻り身支度を整え帰宅します。
この間、約四〜五時間。でも、あっという間に感じます。
この炉の正午の茶事の順を基本に、「朝茶」「前茶」などのバリエーションがあります。
「朝茶」とは、七月や八月の猛暑の昼に客を招くことが無理な時節、五時や六時の早朝から九時〜十時、日が高くなる前の「夏の涼気を楽しむ」という心意気から生まれたもの。
暑気払いの効果や、暑い季節だからこその道具やしつらえを味わい、季節とともに歩むのを楽しむ茶事です。
特徴として、夏の早朝、釜に清新な朝の水をつぐという所作、懐石の料理も夏の朝ですから、焼き物は省き生の魚は使わない「一汁二菜」。
丁寧で正式を軸に 朝茶では、「初炭」「懐石」「菓子・中立ち」「濃茶・続き薄茶」という順序で、「後炭」を省略し、濃茶と薄茶を続けて点てることで時間を短縮し、サラサラと進めることが信条です。
夏のご馳走は「水」。亭主は、前夜からしっかりと道や露地に水を打ち、準備を始めます。
お客様には マイナスイオンたっぷりの露地や、夏ならではの道具の取り合わや花、献立を楽しみ、メインである濃茶を皆で味わっていただきたいです。
普段の稽古はこの「茶事」を楽しむ作法や心を学ぶもの。ですから、茶事は稽古の集大成。とはいえ この茶事は、どの段階でも客として楽しむことができます。本当の「日本のおもてなし」を体感できます。
今夏は、稽古社中は勿論、懐石料理を協力していただいいる割烹料理店の若手スタッフ三名、昨年からタイに転勤している華道の弟子、主人が経営するスペインレストランへアルバイトで来ている交換留学生のスペイン人女性と体験の方も大勢参加します。私はまさに今、準備に追われていますが、この生みの苦しみ無くして 成功はないので頑張ります!
「茶の湯こそ せぬひともなき手すさみの 心のするは世にもまれなり」/道安(利休の息子)
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/茶道教室-華道教室-438381252917488/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
「七夕」って?
2016年8月19日 Category: 茶道のお知らせ
立秋の暦が過ぎたとはいえ、暑さはピークを迎えていますね。
先週、朝方の涼を楽しむ我が家の「朝茶事」が、無事終了しました。
このホームページにも書いていますが、『茶事(ちゃじ)』とは、茶の湯の集大成。
普段の稽古は、点前の稽古をはじめとして、立ち居ふるまい全て、茶事をよりよく催すためにあるのです。 いわば茶事は、「本番」 。
たった今、リオで開催されているオリンピックとは、「この本番の一瞬に生きる」というところが似ています。 今 活躍しているどの選手にせよ長い永い年月の集大成がこの “一瞬” に集結するわけですからね。(もっとも、その練習量などは比べられるものではありませんが。)
茶の湯の世界は、順位を競うわけではないので、初心者から上級者まで どの段階にあっても、それぞれに楽しめて 一緒にその場を造りあげることが出来ます。
さて、この茶事の形式が定まったのは 利休の時代。 その頃は「茶会」、または単に「会」と呼ばれていました。「会」という名で色々な趣旨の会の記録が残っています。その多くは四畳半以下の茶席で、濃茶をもてなすことを主な目的としたものでした。
亭主の趣向で いつ、どのように開いてもよい「茶事」。その中心に“抹茶”が あります。
さて、今年の朝茶のテーマは 『七夕』。
「え? 七夕って、七月では?」と、思った貴方。 勿論、七夕は 七月七日。でも、、私が仙台に住んでいた頃も今も 地方では八月七〜八日で行なわれていますね、 「これは、ただ旧暦ってことなのかしら?」 と 長い間不思議に思っていました。
実は今回、長年憧れていた 「糸巻爪紅二重棚」 を入手。
このお披露目を「朝茶」で と思案したとき、以前 華道の古典立花教室で私が卒業論文に取りくんだ “いけばなの起源「七」という数字” に「七夕」の記載があったのを思い出しました。
(高橋 睦郎さんが とてもわかりやすく 今月号の華道冊子に書いていましたので引用させて頂きます。)
 (写真は七夕のお菓子「梶の葉」)
(写真は七夕のお菓子「梶の葉」)
現在、七夕は七月七日に祭るところが多いようだが、本来は旧暦で現行の歴で今年は八月九日。それも六日夜から翌七日にかけてというのが正しい。
七夕をタナバタと訓むのはもちろん当て字。 もともと中国の五節句の一つである七夕(しちせき)と、わが国古来の夏秋の交叉(ゆきあい=交わり移り変わるころの意)の祭行事タナバタとは別。
タナバタは、初秋に訪れると考えられた神を迎えるために、水のほとりなどに張り出した棚を作り、その上で処女が神の妻として、神に着せる聖衣を織った。棚の上で機(はた)を織るから棚機(たなばた)、その処女を 棚機(たなばた)つ女(め)、後には「棚機姫」と云った。
そこに中国の暦とともに七夕の行事が伝わり、七夕伝説の牽牛星(けんぎゅうせい)が訪れる神に、織女星が神の訪れを待ち設ける棚機姫に重ね合わされて、かの地の乞巧奠(きこうてん=少女たちが機織りなどの手仕事が巧みになるように乞い願う奠(まつり))が日本化して 星祭りの風習が生まれた。
かつて 七夕竹は、迎えた神が翌朝帰って行くときに自分たちの罪穢れを持っていってくれることを願って川や海に流したのが起こりで、「星送り」のためが正確らしい。
現在は、衛生上もあって流すことが少なくなり、七夕本来の意味がわからなくなった。
、とのこと。
『夏秋の交叉(ゆきあい)』・・なんて素敵な表現でしょう。
今年は、八月七日が「立秋」。 “夏の名残” と、 “秋の兆し” が交叉う頃、その時 神様が降りてきてくださる・・なんてロマンチックな奠(まつり)なのでしょう !
テレビでは毎日、『何度です。熱中症に気をつけてください! 』 と連呼されていて、確かに非常に暑いです。
ですが、そんな物語とともに「夏秋の交叉」を今回の「朝茶」で体験したメンバーにとっては 頭の中は もう “初秋” に切り替わっているはず。
心の切り換えって、とっても不思議。
先月「七夕」について知りたくなり、中国からの留学生の生徒に <中国での七夕の行事と、現在の七夕の過ごしてかた > を尋ねたところ、『七夕の起源は知りませんし、特に何もしません。若いカップルにとっては、デートの日です♡』 とのこと。
牽牛・織女の七夕伝説。 七夕の飾りが風にゆれるように、恋の気分もゆらゆら なびく?
・・そんな 日本の ゆかしい風習。大切にしたいものですね。
七夕に頂く「梶の葉」のお話もしなくてはいけませんね。
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
先週、朝方の涼を楽しむ我が家の「朝茶事」が、無事終了しました。
このホームページにも書いていますが、『茶事(ちゃじ)』とは、茶の湯の集大成。
普段の稽古は、点前の稽古をはじめとして、立ち居ふるまい全て、茶事をよりよく催すためにあるのです。 いわば茶事は、「本番」 。
たった今、リオで開催されているオリンピックとは、「この本番の一瞬に生きる」というところが似ています。 今 活躍しているどの選手にせよ長い永い年月の集大成がこの “一瞬” に集結するわけですからね。(もっとも、その練習量などは比べられるものではありませんが。)
茶の湯の世界は、順位を競うわけではないので、初心者から上級者まで どの段階にあっても、それぞれに楽しめて 一緒にその場を造りあげることが出来ます。
さて、この茶事の形式が定まったのは 利休の時代。 その頃は「茶会」、または単に「会」と呼ばれていました。「会」という名で色々な趣旨の会の記録が残っています。その多くは四畳半以下の茶席で、濃茶をもてなすことを主な目的としたものでした。
亭主の趣向で いつ、どのように開いてもよい「茶事」。その中心に“抹茶”が あります。
さて、今年の朝茶のテーマは 『七夕』。
「え? 七夕って、七月では?」と、思った貴方。 勿論、七夕は 七月七日。でも、、私が仙台に住んでいた頃も今も 地方では八月七〜八日で行なわれていますね、 「これは、ただ旧暦ってことなのかしら?」 と 長い間不思議に思っていました。
実は今回、長年憧れていた 「糸巻爪紅二重棚」 を入手。
このお披露目を「朝茶」で と思案したとき、以前 華道の古典立花教室で私が卒業論文に取りくんだ “いけばなの起源「七」という数字” に「七夕」の記載があったのを思い出しました。
(高橋 睦郎さんが とてもわかりやすく 今月号の華道冊子に書いていましたので引用させて頂きます。)
 (写真は七夕のお菓子「梶の葉」)
(写真は七夕のお菓子「梶の葉」)
現在、七夕は七月七日に祭るところが多いようだが、本来は旧暦で現行の歴で今年は八月九日。それも六日夜から翌七日にかけてというのが正しい。
七夕をタナバタと訓むのはもちろん当て字。 もともと中国の五節句の一つである七夕(しちせき)と、わが国古来の夏秋の交叉(ゆきあい=交わり移り変わるころの意)の祭行事タナバタとは別。
タナバタは、初秋に訪れると考えられた神を迎えるために、水のほとりなどに張り出した棚を作り、その上で処女が神の妻として、神に着せる聖衣を織った。棚の上で機(はた)を織るから棚機(たなばた)、その処女を 棚機(たなばた)つ女(め)、後には「棚機姫」と云った。
そこに中国の暦とともに七夕の行事が伝わり、七夕伝説の牽牛星(けんぎゅうせい)が訪れる神に、織女星が神の訪れを待ち設ける棚機姫に重ね合わされて、かの地の乞巧奠(きこうてん=少女たちが機織りなどの手仕事が巧みになるように乞い願う奠(まつり))が日本化して 星祭りの風習が生まれた。
かつて 七夕竹は、迎えた神が翌朝帰って行くときに自分たちの罪穢れを持っていってくれることを願って川や海に流したのが起こりで、「星送り」のためが正確らしい。
現在は、衛生上もあって流すことが少なくなり、七夕本来の意味がわからなくなった。
、とのこと。
『夏秋の交叉(ゆきあい)』・・なんて素敵な表現でしょう。
今年は、八月七日が「立秋」。 “夏の名残” と、 “秋の兆し” が交叉う頃、その時 神様が降りてきてくださる・・なんてロマンチックな奠(まつり)なのでしょう !
テレビでは毎日、『何度です。熱中症に気をつけてください! 』 と連呼されていて、確かに非常に暑いです。
ですが、そんな物語とともに「夏秋の交叉」を今回の「朝茶」で体験したメンバーにとっては 頭の中は もう “初秋” に切り替わっているはず。
心の切り換えって、とっても不思議。
先月「七夕」について知りたくなり、中国からの留学生の生徒に <中国での七夕の行事と、現在の七夕の過ごしてかた > を尋ねたところ、『七夕の起源は知りませんし、特に何もしません。若いカップルにとっては、デートの日です♡』 とのこと。
牽牛・織女の七夕伝説。 七夕の飾りが風にゆれるように、恋の気分もゆらゆら なびく?
・・そんな 日本の ゆかしい風習。大切にしたいものですね。
七夕に頂く「梶の葉」のお話もしなくてはいけませんね。
日々の稽古や、生徒の作品、ワークショップの様子などをF.B.に(たまに)アップしています。 https://www.facebook.com/
西武新宿線沿 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
茶道 納会
2016年1月3日 Category: 茶道のお知らせ
「師走」とは、よく云ったものだと毎年苦笑いしながら、走っている歳の瀬。
そんな、だれもが忙しなく追われる年末でも、稽古社中が集まり、
今年も「無事」に過ごす事ができたことを祝うのが「納会」。
家元では「今年先無事千秋楽」という掛物を掛けるそうです。
臨済録にある『無事』についての語は、意味深く 興味のある方は調べてみることをお勧めします。(禅語は、説明不可能なので。私なりに調べたてみたら、こんなページがありました。
参考までに→ http://www.rinnou.net/cont_04/zengo/051201.html
その「無事」という言葉を噛み締めながら、我が家の納会では七事の一つ『廻り炭』をし、
『お伽(おとぎ)』と呼ばれる精進で一献祝い膳を出し皆で囲みます。
『廻り炭』とは、炭点前のときの『火の相』を学ぶ七事。一人ひとり廻り合って炭をつぎ炭について学びます。
精進膳での一献は、私も入り社中皆で和みの会です。
定例の献立は『渦み豆腐』。木綿豆腐の上にお米(雪)、大根を丸く(月)、京人参を花に例えて。青菜と海苔も添え、この上に白味噌汁をかけたもの。これは、禅寺のけんちん汁をお茶人風にアレンジしたものだそう。正式にはご飯と味噌汁を別々に装うのだけど、この時期ならではの茶道人の粋な工夫に感動します。
そして『鰯煮』と、『柚子砂糖浸』(ここ何年か京都「水尾の柚子」を分けていただいているので、超 美味!)。また紅白膾など。
今年は、何故か急に「胡麻豆腐」が作りたくなり挑戦!なんとか 大好評?
作ってみて実感。決して難しくないのだけれど、確かにこれは修行になります。兎に角、目が離せない。腕を振るい続ける!体力勝負。今年自作の味噌を薄めて敷き、摺り生姜のせて。
毎年、同じ事を繰り返す事の大切さを しみじみ感じる年末年始。
倒れそう・・思うことも あるけれど、それさえも 幸せなことと思います。
このブログも、ようやく更新できました。感謝します。
こんな わたしですが、今年もよろしくお願いいたします。
皆様も、素敵な一年になりますように。お祈りいたします。
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
そんな、だれもが忙しなく追われる年末でも、稽古社中が集まり、
今年も「無事」に過ごす事ができたことを祝うのが「納会」。
家元では「今年先無事千秋楽」という掛物を掛けるそうです。

臨済録にある『無事』についての語は、意味深く 興味のある方は調べてみることをお勧めします。(禅語は、説明不可能なので。私なりに調べたてみたら、こんなページがありました。
参考までに→ http://www.rinnou.net/cont_04/zengo/051201.html
その「無事」という言葉を噛み締めながら、我が家の納会では七事の一つ『廻り炭』をし、
『お伽(おとぎ)』と呼ばれる精進で一献祝い膳を出し皆で囲みます。
『廻り炭』とは、炭点前のときの『火の相』を学ぶ七事。一人ひとり廻り合って炭をつぎ炭について学びます。

精進膳での一献は、私も入り社中皆で和みの会です。
定例の献立は『渦み豆腐』。木綿豆腐の上にお米(雪)、大根を丸く(月)、京人参を花に例えて。青菜と海苔も添え、この上に白味噌汁をかけたもの。これは、禅寺のけんちん汁をお茶人風にアレンジしたものだそう。正式にはご飯と味噌汁を別々に装うのだけど、この時期ならではの茶道人の粋な工夫に感動します。
そして『鰯煮』と、『柚子砂糖浸』(ここ何年か京都「水尾の柚子」を分けていただいているので、超 美味!)。また紅白膾など。

今年は、何故か急に「胡麻豆腐」が作りたくなり挑戦!なんとか 大好評?
作ってみて実感。決して難しくないのだけれど、確かにこれは修行になります。兎に角、目が離せない。腕を振るい続ける!体力勝負。今年自作の味噌を薄めて敷き、摺り生姜のせて。

毎年、同じ事を繰り返す事の大切さを しみじみ感じる年末年始。
倒れそう・・思うことも あるけれど、それさえも 幸せなことと思います。
このブログも、ようやく更新できました。感謝します。
こんな わたしですが、今年もよろしくお願いいたします。
皆様も、素敵な一年になりますように。お祈りいたします。
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
『 道 と 私 』
2015年11月7日 Category: 茶道のお知らせ
私の茶道教室では「蓮心会」という会をつくり、社中で企画・運営しています。
日々の稽古以外にも、幅広く茶道の見識を広げたいとの思いから発足しました。
茶道を学ぶ者にとって大切な『茶事』をはじめ、『利休忌』『天然忌』『納会』は勿論、『お許しの研究会』、茶道を軸に それぞれ学びたいことをピックアップしての勉強会や、『お能のワークショップ』『野点の会』『着付けアドバイス』など、皆で相談しながら活動しています。
今年は、5月に『懇親会』を開きました。会場は、毎回「茶事」でお世話になっている
新宿「菊うら」さん。とても美味しい割烹料理屋さんです。
さて、ただの「懇親会」だけにしないところが、流石、『蓮心会』!
今回は、『道と私』という題で、それぞれの「道」を通して 感じたこと、その思いを原稿用紙 1〜2枚で、発表するという企画。お食事の前に、各自(持ち時間1~2分)発表です。

皆さんが、「道」を通して感じた正直で素晴らしい文章に、感動。
そして「菊うら」さんでの素晴らしく美味しいお料理にも、感動。

お食事の後には、新宿御苑を探索し、お茶室で抹茶を一服しました。
そして!その 21名のそれぞれの「道」を学んで気が付いたこと、感じたこと、これからの思いが綴られた冊子が出来上がりました。茶道 17名、華道 3名、能楽師 1名。
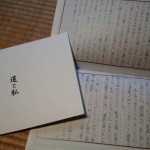
・『(略)僕は、習い事は経験したことがなく、大人達がいっぱいでどうゆう風に大人達と接すればよいのかわからず嫌になってすぐやめてしまうと思いました。しかし、(略)これからも茶道を続けてたくさんの作法を身につけ、かっこいいお点前でみなさんに恩返しできるように精一杯がんばります。(略)』小学5年から初めた男子、来年高校受験。
・『(略)僕は外国についてしりたがるくせして、日本のことについては何も知らないのだということに気づきました。(略)いざ始めてみると、僕のイメージとは違う世界がそこにはありました。周りへの気遣いも大切だけども、場の雰囲気を固くしないようにする、そして何よりもそれに対する臨機応変な対応が客に必要なんだということが、一番の衝撃でした。(略)こうした互いを思いやる気持ちや、お茶を点てる側になった時のおもてなしの心が、日本人として大切なんだということがわかりました。(略)』中学2年生のお兄さん、来年大学受験。
・『(略)大切なことは、技術の上手い下手などではなく、相手に対してどうゆう気持ちで、どのような思いで接するか、ということであり、茶道という一つの手段を媒介とした人と人とのコミュニケーションこそ学ばなくてはならないということです。(略)』茶道を学ぶなかで、もう一度医学部へ大学受験をし直す覚悟を決めた大学生。
・『仕事の為になると思い、茶道を学びはじめた(略)。』建築設計師。
・『日常から離れ、静かに畳に吸わす時間で、気持ちをリセットしたい(略)。』主婦。
・『着物を着たくて始めた、(略)。』女子。
・『緊張感とともに、五感が冴えた状態が心地よいことに驚かされた。(略)』編集職。
・『静けさや平坦さのなかに、ハッとするような自由な動(変化)が取りこまれるというのは、日本文化に特徴的な魅力なのかもしれない。(略)』アロマテラピーのプロ。
・『茶道とは心の持ちようを修行する場である。(略)』着物のプロ。
・『障子を閉める際の陰陽の変化が、今でも目の奥に焼きついています。(略)「茶道」は、女性がするものと思っていたが、歴史や道具を見て学ぶうちに、むしろこの世界は男の世界で大成されたのだと考えるようになりました。(略)』塗装業男子。
・『どんなコンディションの時であっても、稽古の帰り道は身も心も軽やかに、次へのやる気がみなぎってくる。稽古場はそんな場所です。(略)』育児と仕事を両立中。
・『時間のゆとりはなくとも心の安寧を保つ術や、人の動きを見守り、必要な行動をとることを学んでいます。(略)』看護婦。
・『型を身につけ、ちっぽけなおごりをそぎ落とす。ただ稽古を繰り返し、教えに忠実になった頃、目の前に自由な世界が広がりました。(略) 謙虚になる事、相手を慮る事は島国ならではの日本人の素晴らしい個性という事。茶の湯を楽しめる美意識は誇れる国民性。(略)』華道、茶道 社中。
・『私にとっていけばなは「感謝」です。いけばなを学ばせていただけるのは多くの人のお陰であると常に感じています。(略) 切磋琢磨し、考え方や姿勢を刺激し合える仲間達がいるからこそ、自分自身を見つめ直し、ものの考え方や感じる心をより豊かにすることができます。(略)』華道社中。
・『草木花との一体感。(略)自らの想念を消して、自然と向き合うことが叶った時、私も自然の一部になれるような気がするのです。(略)』華道社中。
・『茶禅一味とは、(略)普通の生活をしているときも、お茶の稽古と同じ所作や心持ちでいるということに気をつけるようになりました。(略)』裏千家友人。
・『何か一つでも能を見て心地よいと感じる事が出来たのならば、それは昔の人と心が通じ合った証拠であり、それこそが能の最大の魅力であると思っております。茶道の世界でも同じ事が言えるのではないかと私は感じました。(略)』能楽師。
とても全てを書ききれないので、省略ばかりで すみません。全員分でもありません。
一冊にまとまったこの冊子は、30年茶道 華道を続けてきたこれまでの私の鏡でもありました。
私も、「先生」の立場からではなく、この「道」によせる想いをつづりました。
『乗り越えるのが困難に思えたいくつもの壁、また時に回り道したことも、茶道の精神の教えを学ぶために欠かせなかった大切なプロセスだったと思います。 ひとつ一つは、点のような小さな出来事でしたが、それを一歩一歩積み重ねて、自分ならではの一本の道を作って来たように思います。』
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
日々の稽古以外にも、幅広く茶道の見識を広げたいとの思いから発足しました。
茶道を学ぶ者にとって大切な『茶事』をはじめ、『利休忌』『天然忌』『納会』は勿論、『お許しの研究会』、茶道を軸に それぞれ学びたいことをピックアップしての勉強会や、『お能のワークショップ』『野点の会』『着付けアドバイス』など、皆で相談しながら活動しています。
今年は、5月に『懇親会』を開きました。会場は、毎回「茶事」でお世話になっている
新宿「菊うら」さん。とても美味しい割烹料理屋さんです。
さて、ただの「懇親会」だけにしないところが、流石、『蓮心会』!
今回は、『道と私』という題で、それぞれの「道」を通して 感じたこと、その思いを原稿用紙 1〜2枚で、発表するという企画。お食事の前に、各自(持ち時間1~2分)発表です。

皆さんが、「道」を通して感じた正直で素晴らしい文章に、感動。
そして「菊うら」さんでの素晴らしく美味しいお料理にも、感動。

お食事の後には、新宿御苑を探索し、お茶室で抹茶を一服しました。
そして!その 21名のそれぞれの「道」を学んで気が付いたこと、感じたこと、これからの思いが綴られた冊子が出来上がりました。茶道 17名、華道 3名、能楽師 1名。
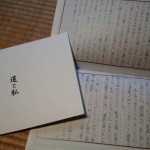
・『(略)僕は、習い事は経験したことがなく、大人達がいっぱいでどうゆう風に大人達と接すればよいのかわからず嫌になってすぐやめてしまうと思いました。しかし、(略)これからも茶道を続けてたくさんの作法を身につけ、かっこいいお点前でみなさんに恩返しできるように精一杯がんばります。(略)』小学5年から初めた男子、来年高校受験。
・『(略)僕は外国についてしりたがるくせして、日本のことについては何も知らないのだということに気づきました。(略)いざ始めてみると、僕のイメージとは違う世界がそこにはありました。周りへの気遣いも大切だけども、場の雰囲気を固くしないようにする、そして何よりもそれに対する臨機応変な対応が客に必要なんだということが、一番の衝撃でした。(略)こうした互いを思いやる気持ちや、お茶を点てる側になった時のおもてなしの心が、日本人として大切なんだということがわかりました。(略)』中学2年生のお兄さん、来年大学受験。
・『(略)大切なことは、技術の上手い下手などではなく、相手に対してどうゆう気持ちで、どのような思いで接するか、ということであり、茶道という一つの手段を媒介とした人と人とのコミュニケーションこそ学ばなくてはならないということです。(略)』茶道を学ぶなかで、もう一度医学部へ大学受験をし直す覚悟を決めた大学生。
・『仕事の為になると思い、茶道を学びはじめた(略)。』建築設計師。
・『日常から離れ、静かに畳に吸わす時間で、気持ちをリセットしたい(略)。』主婦。
・『着物を着たくて始めた、(略)。』女子。
・『緊張感とともに、五感が冴えた状態が心地よいことに驚かされた。(略)』編集職。
・『静けさや平坦さのなかに、ハッとするような自由な動(変化)が取りこまれるというのは、日本文化に特徴的な魅力なのかもしれない。(略)』アロマテラピーのプロ。
・『茶道とは心の持ちようを修行する場である。(略)』着物のプロ。
・『障子を閉める際の陰陽の変化が、今でも目の奥に焼きついています。(略)「茶道」は、女性がするものと思っていたが、歴史や道具を見て学ぶうちに、むしろこの世界は男の世界で大成されたのだと考えるようになりました。(略)』塗装業男子。
・『どんなコンディションの時であっても、稽古の帰り道は身も心も軽やかに、次へのやる気がみなぎってくる。稽古場はそんな場所です。(略)』育児と仕事を両立中。
・『時間のゆとりはなくとも心の安寧を保つ術や、人の動きを見守り、必要な行動をとることを学んでいます。(略)』看護婦。
・『型を身につけ、ちっぽけなおごりをそぎ落とす。ただ稽古を繰り返し、教えに忠実になった頃、目の前に自由な世界が広がりました。(略) 謙虚になる事、相手を慮る事は島国ならではの日本人の素晴らしい個性という事。茶の湯を楽しめる美意識は誇れる国民性。(略)』華道、茶道 社中。
・『私にとっていけばなは「感謝」です。いけばなを学ばせていただけるのは多くの人のお陰であると常に感じています。(略) 切磋琢磨し、考え方や姿勢を刺激し合える仲間達がいるからこそ、自分自身を見つめ直し、ものの考え方や感じる心をより豊かにすることができます。(略)』華道社中。
・『草木花との一体感。(略)自らの想念を消して、自然と向き合うことが叶った時、私も自然の一部になれるような気がするのです。(略)』華道社中。
・『茶禅一味とは、(略)普通の生活をしているときも、お茶の稽古と同じ所作や心持ちでいるということに気をつけるようになりました。(略)』裏千家友人。
・『何か一つでも能を見て心地よいと感じる事が出来たのならば、それは昔の人と心が通じ合った証拠であり、それこそが能の最大の魅力であると思っております。茶道の世界でも同じ事が言えるのではないかと私は感じました。(略)』能楽師。
とても全てを書ききれないので、省略ばかりで すみません。全員分でもありません。
一冊にまとまったこの冊子は、30年茶道 華道を続けてきたこれまでの私の鏡でもありました。
私も、「先生」の立場からではなく、この「道」によせる想いをつづりました。
『乗り越えるのが困難に思えたいくつもの壁、また時に回り道したことも、茶道の精神の教えを学ぶために欠かせなかった大切なプロセスだったと思います。 ひとつ一つは、点のような小さな出来事でしたが、それを一歩一歩積み重ねて、自分ならではの一本の道を作って来たように思います。』
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
天然忌
2015年10月8日 Category: 茶道のお知らせ
天然忌とは、表千家七代家元の天然宗左「如心斎」を追善する、大事な行事です。
『表千家』『裏千家』『武者小路千家』は、千利休から数えて四代目から分かれます。
なので天然忌は、表千家だけの法事。表千家の中興の祖と云われる如心斎の徳を偲ぶ大切な日です。家元では九月十三日に催されます。
如心斎(1705~1751年)の大きな功績の一つに、『七事式』を定められたことがあります。
江戸時代、政治も安定し茶道人口も増えた時代に、小間での茶を中心としたわび茶に広間での茶を取り込んで、八畳の広間で五人以上が稽古する七つの式法です。
『花月』『旦座』『茶かぶき』『まわり炭』『まわり花』『一二三』『数茶』の七つの稽古法で、弟の一燈宗室(裏千家)、高弟の川上不白などと、相談して決めたと伝えられています。
我が家の天然忌は、床の間に「円相」の掛物をかけ、矢筈板の青磁の花入には 秋明菊を飾ります。先ずは如心斎に「うずら餅」をお供えし、「供茶」をします。その後我々も抹茶をいただきます。

そして、七事の中から『旦座(さざ)』。これは、五人それぞれの役を担って行なう式法。
『是法住法位』(客となれば客、主となれば主)。
正客が花を生け、二客が炭をつぎ、三客が香を焚く、東が亭主役、半東は全ての準備を担います。
まるで『茶事』のダイジェスト版のようで、本当に良く出来ている式法だと毎回感動します。
写真は、その時に使う「旦座盆(香盆)」と、「実菓子」。山で手に入れた葉付の柿が見応え満点!


日曜日は、続けて『まわり花』も皆で楽しみました。
年に一回の大切な行事。その中に先人の豊かな知恵や教えが沢山あります。
毎回の稽古を大切に重ねていきたいと改めて感じた一日でした。
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
『表千家』『裏千家』『武者小路千家』は、千利休から数えて四代目から分かれます。
なので天然忌は、表千家だけの法事。表千家の中興の祖と云われる如心斎の徳を偲ぶ大切な日です。家元では九月十三日に催されます。
如心斎(1705~1751年)の大きな功績の一つに、『七事式』を定められたことがあります。
江戸時代、政治も安定し茶道人口も増えた時代に、小間での茶を中心としたわび茶に広間での茶を取り込んで、八畳の広間で五人以上が稽古する七つの式法です。
『花月』『旦座』『茶かぶき』『まわり炭』『まわり花』『一二三』『数茶』の七つの稽古法で、弟の一燈宗室(裏千家)、高弟の川上不白などと、相談して決めたと伝えられています。
我が家の天然忌は、床の間に「円相」の掛物をかけ、矢筈板の青磁の花入には 秋明菊を飾ります。先ずは如心斎に「うずら餅」をお供えし、「供茶」をします。その後我々も抹茶をいただきます。

そして、七事の中から『旦座(さざ)』。これは、五人それぞれの役を担って行なう式法。
『是法住法位』(客となれば客、主となれば主)。
正客が花を生け、二客が炭をつぎ、三客が香を焚く、東が亭主役、半東は全ての準備を担います。
まるで『茶事』のダイジェスト版のようで、本当に良く出来ている式法だと毎回感動します。
写真は、その時に使う「旦座盆(香盆)」と、「実菓子」。山で手に入れた葉付の柿が見応え満点!


日曜日は、続けて『まわり花』も皆で楽しみました。
年に一回の大切な行事。その中に先人の豊かな知恵や教えが沢山あります。
毎回の稽古を大切に重ねていきたいと改めて感じた一日でした。
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子
平成27 年度 朝茶
2015年8月29日 Category: 茶道のお知らせ
今年の猛暑は例年以上に厳しかったですね。

8月8日9日、我が家にて恒例の朝茶を開きました。
先人は「暑い夏は、早朝の涼しい時にお茶を楽しみましょう。」と早朝に茶事を開いたとのこと。
その昔は明け方4時頃に集まり、8時頃お開きとの記録があるそうですが、現代では電車の都合もあり、我が家では6時半席入りです。
我が家の朝茶は『続き薄茶』でお招きします。
『続き薄茶』とは、「炭点前」→「茶懐石」→「濃茶から続いて薄茶」というスタイルで、
濃茶と薄茶の間の「後炭」を省略することを意味します。
昔はエアコンもない夏の暑い時期、サラサラっと時間を長引かせない、その季節ならではの
おもてなしの心ですね。
今年の朝茶の「ご馳走」は、『食籠(じきろう)』。表千家で使われるお菓子を入れる器です。
「ご馳走」と云っても、食べ物ではなくて「目や触感」のご馳走。
何年も前、大好きな作家さんに『こういう食籠が欲しいが可能か?』と具体的に話をしていたことをその作家さんが覚えていて下さり、半年程前の展示会に発表してくださったのです。
きっとご苦労があったと思いますが、とても素敵な仕上がりに、大感動。
普段の茶懐石では、食事の最後にデザートである「主菓子」を、一番正式な菓子器である「縁高」を用いますが、今回は朝茶で初お披露目に。この日から我が家のお道具の仲間入りです。
上の写真は、初めの「席入り」のために「蹲(つくばい)」を使っているシーン。
ここで手や口を清めて「席入り」です。
二回目の「席入り」では、床の間に花が飾られ「濃茶・薄茶」をいただきます。
土曜日に真っ白な「鉄線」、日曜日は大切に育てた朝顔の「団十朗」が、見事に開きました。
下の写真は、茶懐石のクライマックス「八寸」を勧めているシーン。
茶事では、『お濃茶』がメインディッシュなので「茶懐石」は、ごくごくシンプルに、素材感を生かしたものが本場ものなのですが、我が家のそれは、美味しくなりすぎてしまうのが、課題です。

8月8日は、立秋。この日を堺に今年ははっきりと風が変わりましたね。
今年は残暑はそれほど厳しくなさそうな予感。
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子

8月8日9日、我が家にて恒例の朝茶を開きました。
先人は「暑い夏は、早朝の涼しい時にお茶を楽しみましょう。」と早朝に茶事を開いたとのこと。
その昔は明け方4時頃に集まり、8時頃お開きとの記録があるそうですが、現代では電車の都合もあり、我が家では6時半席入りです。
我が家の朝茶は『続き薄茶』でお招きします。
『続き薄茶』とは、「炭点前」→「茶懐石」→「濃茶から続いて薄茶」というスタイルで、
濃茶と薄茶の間の「後炭」を省略することを意味します。
昔はエアコンもない夏の暑い時期、サラサラっと時間を長引かせない、その季節ならではの
おもてなしの心ですね。
今年の朝茶の「ご馳走」は、『食籠(じきろう)』。表千家で使われるお菓子を入れる器です。
「ご馳走」と云っても、食べ物ではなくて「目や触感」のご馳走。
何年も前、大好きな作家さんに『こういう食籠が欲しいが可能か?』と具体的に話をしていたことをその作家さんが覚えていて下さり、半年程前の展示会に発表してくださったのです。
きっとご苦労があったと思いますが、とても素敵な仕上がりに、大感動。
普段の茶懐石では、食事の最後にデザートである「主菓子」を、一番正式な菓子器である「縁高」を用いますが、今回は朝茶で初お披露目に。この日から我が家のお道具の仲間入りです。
上の写真は、初めの「席入り」のために「蹲(つくばい)」を使っているシーン。
ここで手や口を清めて「席入り」です。
二回目の「席入り」では、床の間に花が飾られ「濃茶・薄茶」をいただきます。
土曜日に真っ白な「鉄線」、日曜日は大切に育てた朝顔の「団十朗」が、見事に開きました。
下の写真は、茶懐石のクライマックス「八寸」を勧めているシーン。
茶事では、『お濃茶』がメインディッシュなので「茶懐石」は、ごくごくシンプルに、素材感を生かしたものが本場ものなのですが、我が家のそれは、美味しくなりすぎてしまうのが、課題です。

8月8日は、立秋。この日を堺に今年ははっきりと風が変わりましたね。
今年は残暑はそれほど厳しくなさそうな予感。
西武新宿線沿い 西東京市 田無駅より徒歩11分の表千家茶道教室・池坊華道いけばな教室
蓮心会 高森 梨津子